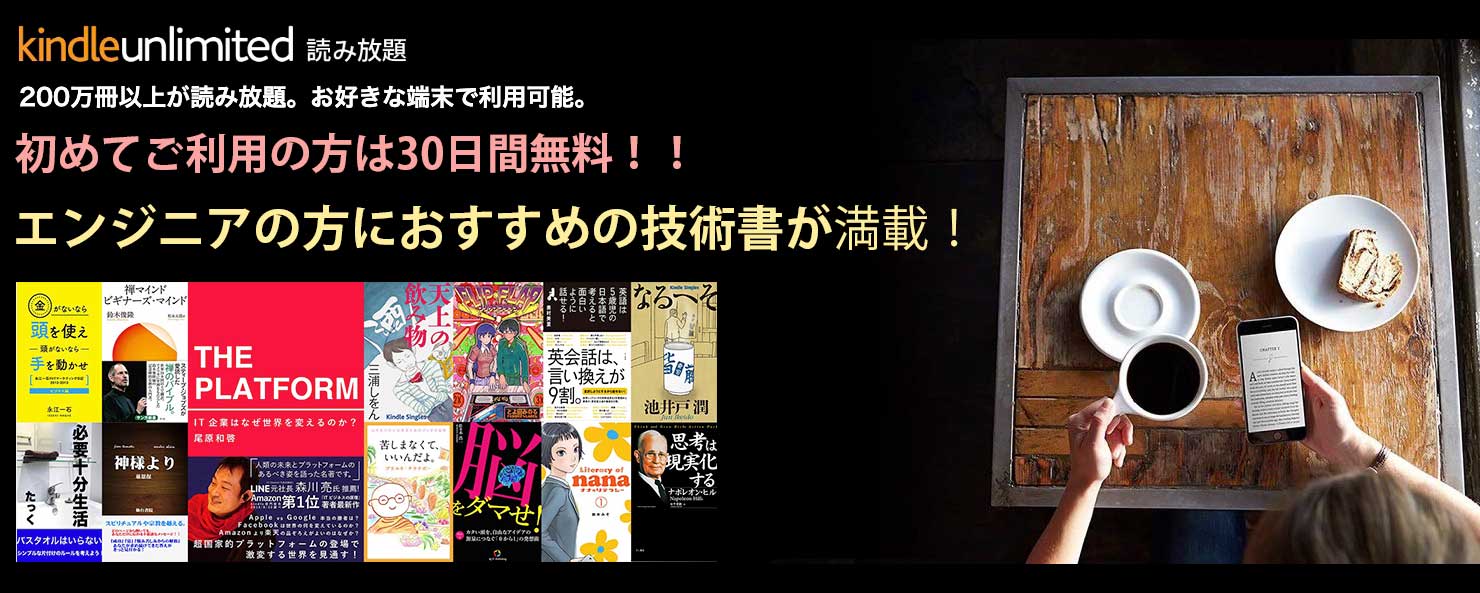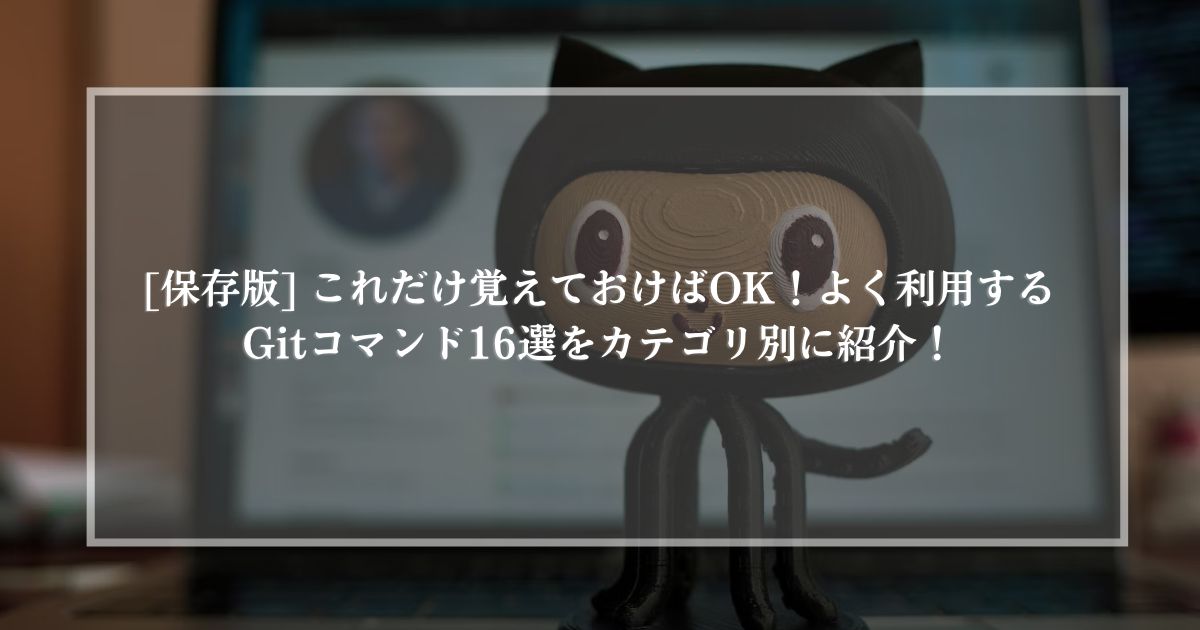フロントエンド開発やバックエンド開発など、JavaScriptでコーディングする場合「try-catch」構文は必ずといっていいほど利用されています。
今回は、このtry-catch文の便利な使い方をご紹介します。
\自身のスキルを向上するには技術書で!!/
月額¥980で技術書が読み放題!!
- ビジネススキルとマインド向上したい!!
- 決断や行動を先送りにしてしまう方!!
全ての例外をcatchする
みなさんがよく利用している一般的な使い方は下記の通りです。
try {
// hogehoge
} catch {
// hogehoge
}これは、「構文エラー」や「ランタイムエラー」、「カスタムエラー」など全ての例外をキャッチします。
ただ、このままの状態だと実際の本番利用で問題が発生した場合、例外の特定が困難なケースも存在します。
特定の例外をcatchする
特定の例外をcatchしたい場合は、catch内で条件を指定します。
try {
// hogehoge
} catch (error) {
if (error instanceof TypeError) {
// hogehoge
}
}または、switch文を利用して、条件のエラーにマッチした処理を行います。
try {
// hogehoge
} catch (error) {
switch (error.constructor) {
case TypeError:
break;
case RangeError:
break;
default:
break;
}
}error.constructorでは、中核となる7つのエラーを得ることができます。
- EvalError
- グローバル関数「eval()」に関して発生するエラー
- InternalError
- JavaScriptエンジンで内部エラーが発生した時に発生するエラー
- RangeError
- 数値や引数が有効範囲外の場合に発生するエラー
- ReferenceError
- 不正な参照先から値を取得した際に発生するエラー
- SyntaxError
- 構文エラー
- TypeError
- 変数や引数の型が有効ではない場合に発生するエラー
- URIError
- encodeURI()やdecodeURI()に不正な引数が渡された際に発生するエラー
非同期処理時の例外をcatchする
非同期処理の例外をcatchする場合は、Promiseを使って例外処理を行う必要があります。
const sample = () => {
return new Promise((resolve, reject) => {
reject(new Error('Exception error occured.'));
});
}
sample().catch(
(error) => console.log(error.message)
);Promiseでは、reject状態のオブジェクトの処理をcatch内で行うことができます。
ですので、try-catchをわざわざ書く必要性がありません。
非同期でエラーとなった場合はcatchメソッドで処理されます。
もし、try-catchで表現したい場合は、下記のようにasync/await を利用して処理します。
const sample = async () => {
throw new Error('Exception error occured.');
}
const result = async () => {
try {
await sample();
// hogehoge
} catch (error) {
// hogehoge
}
};
result();async/await を使って非同期処理をする場合は try-catchも非同期処理する必要があります。
finally を使ってcatch後の処理を行う
ファイル読み書きやDB読み書きなど、リソースのオープン/クローズを行う処理の場合、finally を利用してリソースをクローズします。
const browser = await puppeteer.launch();
try {
// hogehoge
} catch(error) {
// hogehoge
} finally {
browser.close();
}例外をThrowする
例外をスローする場合は下記のように行います。
function sample(b) {
if (b === 1) {
throw new Error("Error occured.");
}
return b;
}上記は通常通り、スローするケースであり、try-catchのcatch側で取得したい場合は、下記のようになります。
try {
// hogehoge
throw new Error('Error occuerd.');
} catch (error) {
console.log (error);
}そもそも例外のスローはどういった時に使うかというと、任意のタイミングで特定のエラーを発生させたい場合に利用します。
try-catch内でThrowすると、catchの引数「error」にthrowで投げた値が格納されます。
例外エラーに対して付加情報を渡す
例外エラーに任意の値を渡すことができます。
try {
const msg = 'A000001'
const code = '403'
throw new Error('Error occuerd.${msg}:${code}')
} catch (error) {
// hogehoge
}例外スローのメッセージ内に出力したい変数を盛り込みます。そうすることで、エラーがより特定しやすくなります。
例外の再スロー
入れ子となったtry-catch文に対して、子try-catch内の例外を親try-catch側に渡したい場合は、子catchブロックないでthrowしてあげます。
try {
try {
throw new Error('Exception error occured.');
} catch (error) {
throw error;
}
} catch (error) {
// hogehoge
}上記のように入れ子側のcatchブロックでthrowしてあげることで、親側のcatchブロック側でエラーを拾ってくれます。
例外エラーをcatchして無視するテクニック
コードのデバッグ中など、例外エラーを無視したい場合があります。
その場合は、catchブロックの中身を「空」にするテクニックがあります。
try {
// hogehogehoge
} catch {
// 何も記述しない
}基本的には、空にすることはおすすめしません。もし、本番稼働時にエラーが発生してもキャッチせず、その後の処理に影響が発生する可能性があります。
window.onerror を使ったcatch処理
try-catchを利用せずに例外をcatchする方法としてwindow.onerrorを使った方法があります。
このwindow.onerrorを用いること、スクリプト内でcatchできなかった例外を検知して通知してくれます。
window.onerror = function(message, source, lineNo, ColNo, error) {
// hogehoge
}- message : エラーメッセージ
- source : エラーが発生したファイルのURL
- lineNo : エラーが発生した箇所の行番号
- colNo : エラーが発生した箇所の列番号
- error : エラーオブジェクト
ただし、古いブラウザではエラーオブジェクトが取得できないので、注意が必要です。
最後に
今回は、JavaScriptでの例外処理を行うためのTipsを9選紹介しました。
これをすべて習得しておけば、基本的な例外処理はすべて問題ないと思います。
是非、ご参考までに。